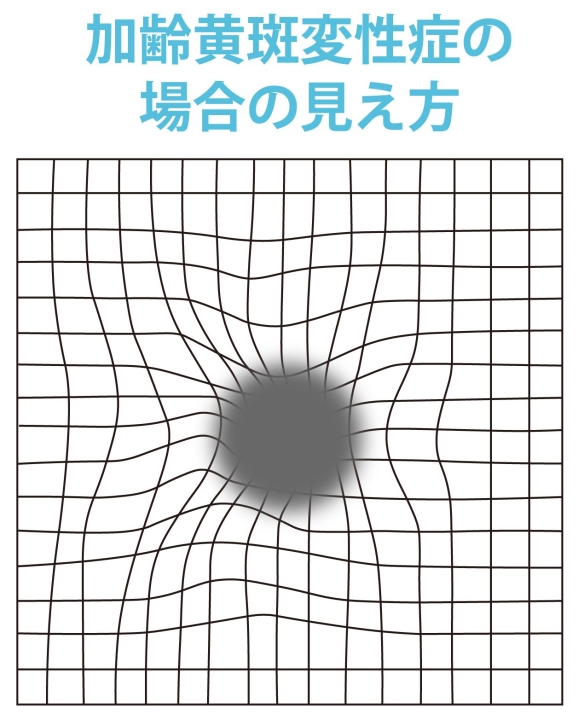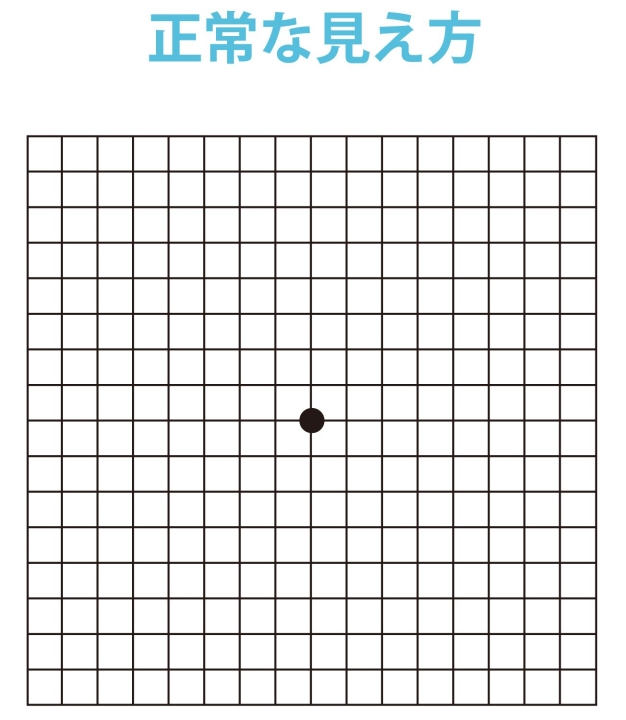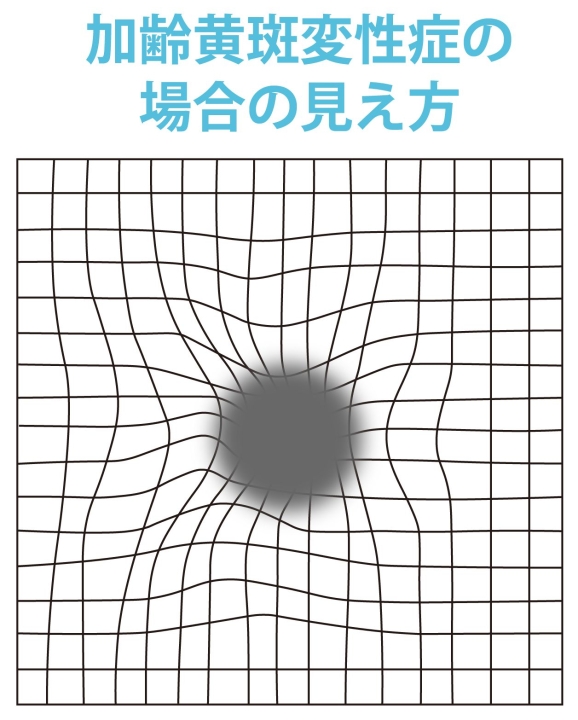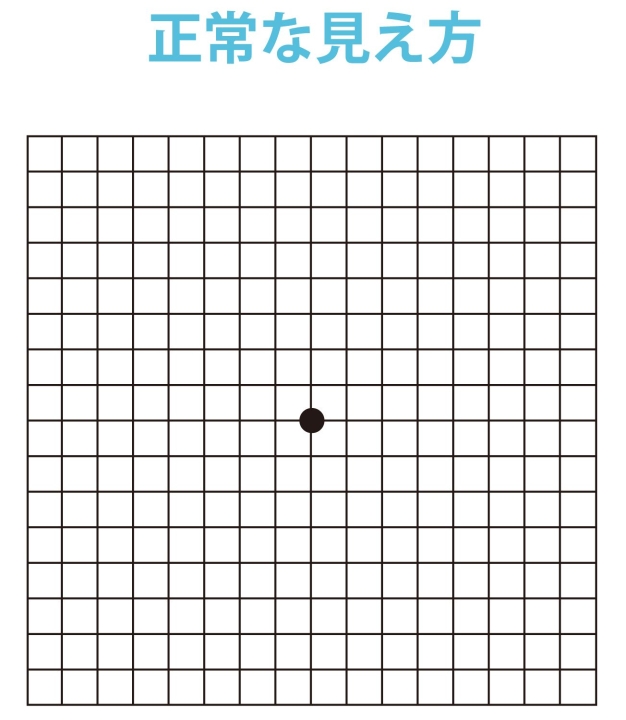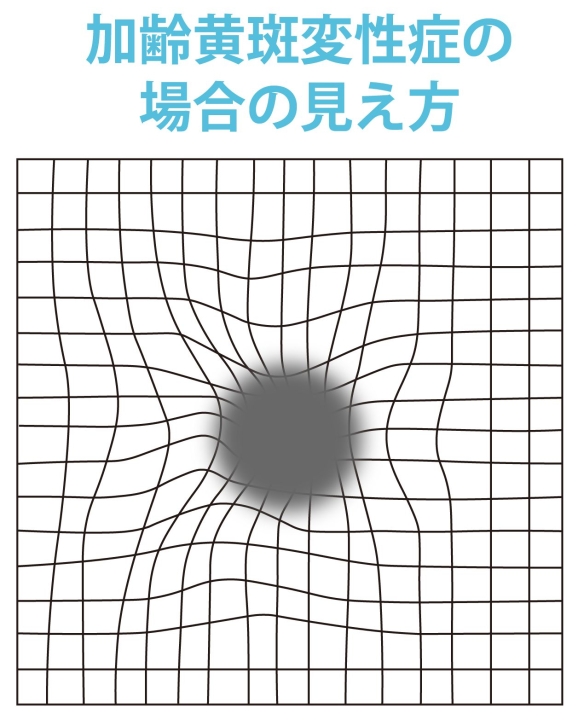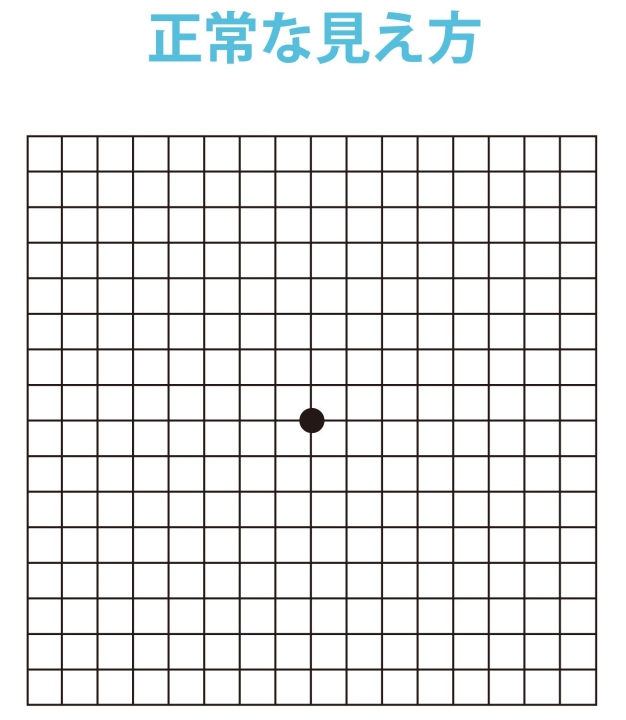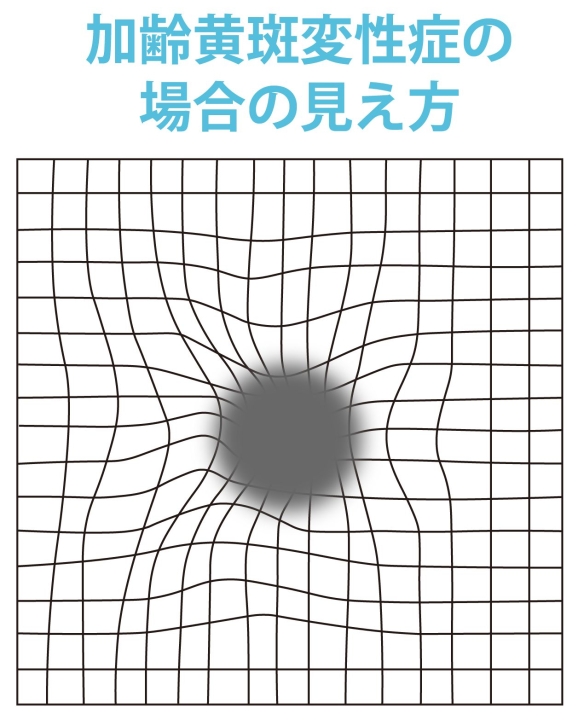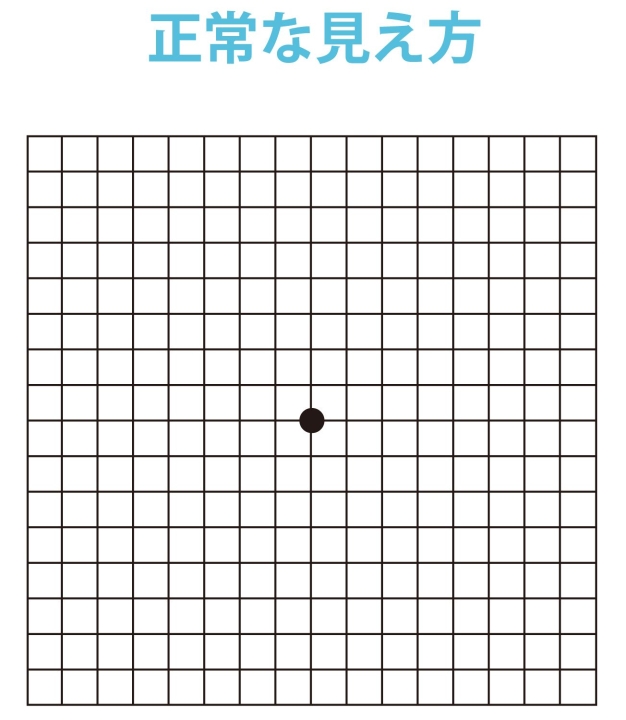👁 加齢黄斑変性症ってどんな病気?
加齢とともに、「黄斑(おうはん)」という網膜の中心部分が傷んでしまう目の病気です。
黄斑は、ものを見るときに一番よく使う場所なので、そこが傷むと
視力に大きな影響が出ます。
⚠ 主な症状(こんな見え方になります)
① 中心が見えにくい・暗く見える
📍 文字の真ん中が読めない
📍 人の顔がぼやけてわからない
② 直線がゆがんで見える
📏 まっすぐな線がグニャッと曲がって見える
(新聞の文字や窓枠など)
③ 視界の一部が欠ける・黒くなる
🔲 見たいところが黒く、もやがかかったように見える
④ 色がわかりにくい・薄く見える
🌈 色の区別がつきにくく、全体にぼんやり
🔍 こんなふうに見えるイメージ
(実際の見え方は人により異なります)
-
🖼【中心だけ見えない】
-
🌀【真ん中がゆがむ・ふくらんで見える】
-
🌫【霧がかかったように見える】
🧠 痛みはない=気づきにくい!
加齢黄斑変性症は、痛みがないうえに両目に徐々に起こることが多く、
初期は気づきにくいのが特徴です。
🚩早期発見がカギ!
-
片目ずつ見え方をチェック
-
「アムスラーチャート」というマス目を使うと便利
-
少しでも違和感があれば、すぐ眼科へ!